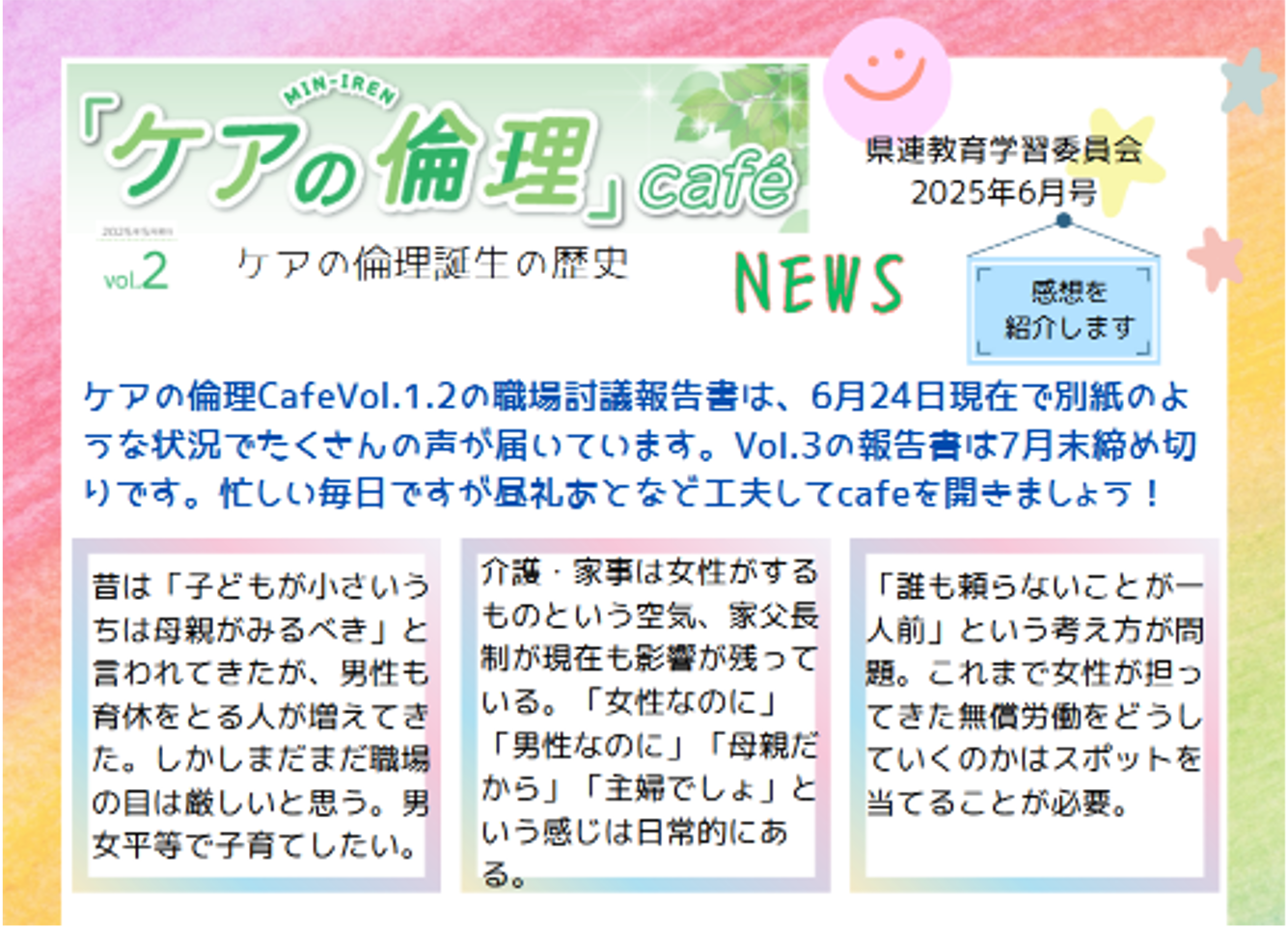先日、高松市の外郭団体である在宅医療介護連携推進会議のミーティングがあったので参加してきました。テーマは『独居高齢者の意思決定支援 ~成功・困難事例を通じて学ぶ~』というものでした。地域でどんどん増えている独居高齢者が、経済的困難、がん、認知症、精神疾患、様々な困難に遭遇し、その方に寄り添った各事業所の支援の取り組みを聞くことができました。こういうところで話を聞くと、なにも平和病院や民医連・医療生協だけが地域でがんばっているんだという思い込みを払拭してくれます。例に出されたよくある話では、独居高齢者のキーパーソンがケアマネージャーになっており、そのケアマネさんが入院先の病院へ洗濯物を取りに行ったり、食べ物の差し入れをしたり、金融機関の取り次ぎをしたり、とみんながそれぞれがんばってるんだなと改めて思いました。
さて、現在民医連では、「ケアの倫理」を深める職場での語り合い(カフェ)を推進しています。今月の平和病院医局でのディスカッションテーマは「資本主義がケアを評価できないと感じることを話してみましょう」というものでした。「資本主義」のとらえ方が人それぞれで、いろいろと意見は出ましたが、聞いていて思ったのは、もうけ第一主義、利潤が出ていなければ社会から即退場の資本主義社会において、もうけにならないこと(上記の独居高齢者のキーパーソン業務など)は周囲からの賞賛、同情を誘うかもしれませんが、あくまで個人の努力によります。もちろん平和病院や医療生協とて、利益を出さなければ職員を引き留めておくことができませんので、効率重視の運営に走らざるを得ない部分もあります。そこにインセンティブを与えるには真逆の方向での政策が行われています。
私たちと他の組織・事業所でなにが違うか考えると、こういった社会の仕組みや矛盾について、正面から向き合い、集団で学習して議論し、おかしいことにはおかしいと声をあげている組織集団であるということではないでしょうか。なので、私たちはみんなで堂々と困っている人に寄り添える、ケアできるしケアされるという関係になれる、ということだと先日のミーティングとカフェを通して考えました。
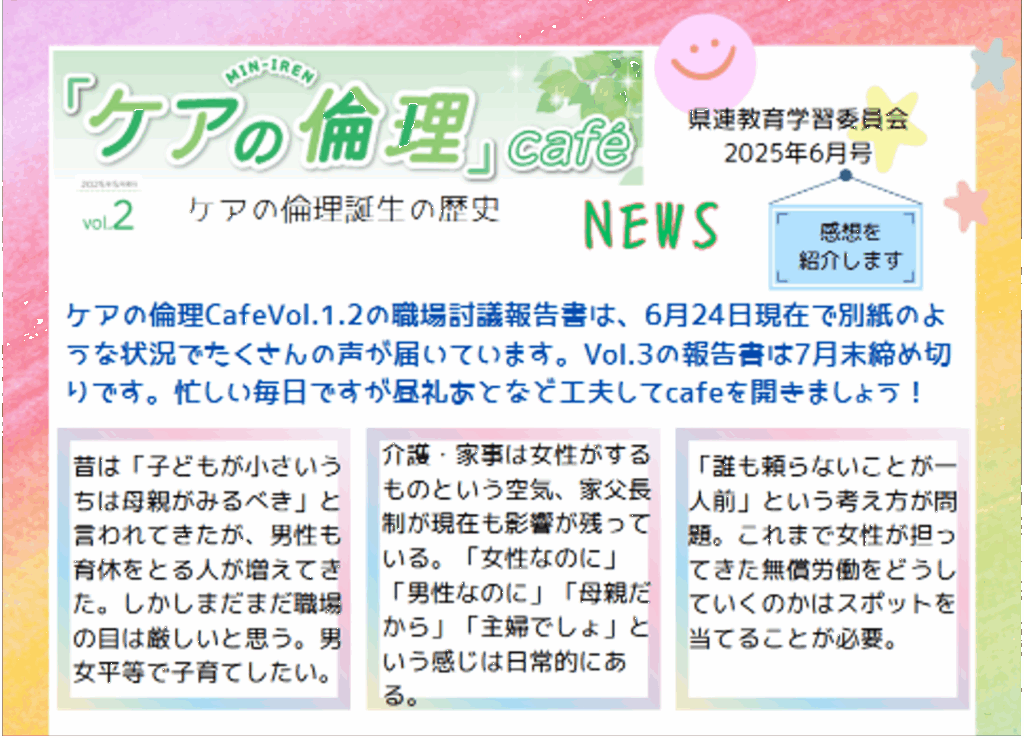
ケアの倫理カフェ
職場討議の感想文の一部を紹介